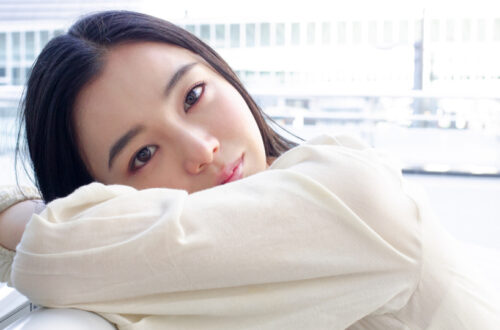コロナが教えてくれたこと
吉川康雄 中川さんはNYのフォトエージェンシー「Art + Commerce」でお仕事されているんですね。僕がニューヨークに移住する時、メイクアップアーティストのエージェントを探していて、最初にブックを見せに行ったのがここなんです。当時ダウンタウンのウェストビレッジにあって、ものすごく素敵なオフィスでめちゃくちゃ憧れちゃいました。何度行っても入れませんでしたが(笑)。今となっては懐かしい思い出です。ここはニューヨークのトップアーティストが集まるところですが、もともとアートに興味があったんですか?
中川玲奈 幼い時から、父がアート好きで、彼の影響が強かったですね。22歳の時に、ニューヨークのプラット・インスティテュートでペインティングを専攻して、もともとはアーティストを志していました。コンセプチュアル・アートにとても興味があって、女性のアーティストが好きで、日本人だとオノ・ヨーコさんをずっと尊敬しています。
吉川 圧倒されますよね。生き方がそのまま表現だから、そこになんの嘘もない。
中川 この間YouTubeで松田聖子さんを見たんですけど、彼女もすごいと思いました。はみ出してるわけではないけれど、自分がやりたいことに素直に生きてますよね。
吉川 中川さんはジャンルを超えていろんな人をアートを見るように見ているんですね。
中川 自分もアーティストになりたかったけれど、なれない(笑)。だからアーティストのお世話をする側にまわって、その人たちがいい撮影ができたり、パフォーマンスができるようにするためのお手伝いをする今の仕事にやりがいを感じています。そして、才能と才能を繋げることが大好きですし、若くて才能のある写真家やアーティストに偶然出会うと、彼らの作品が早く認めてもらえるように頑張っちゃいます。
吉川 アーティストには、中川さんみたいな人が絶対に必要ですもんね。
中川 ちょっと話は変わりますけど、去年コロナでNYがロックダウンになった時に思ったんですけど、ポスターとかファッションとか、そういうものがあの瞬間に、すごくくだらないじゃないけれど……。
吉川 意味ないものに見えてしまった?
中川 あの瞬間に、自分の中でまったく無意味なものになってしまったというか。今でもあの衝撃を覚えています。
吉川 たとえば昔、ロンドンでパンクがファッションになりましたよね。パンクは確実にその時のリアルで、イギリスの貧しい若者たちが不満を持ってやってきた。それが意味なくなると滑稽になるじゃないですか。そういうことなのかな?
中川 そうかもしれないですね。でも1年ぐらいして、時間が経つとまた変わってきていますよね。それこそ、吉川さんがやっていらっしゃることに世の中が近づいている。広告にも、キレイな人だけではなく一般の人を使うようになったり、撮影も家でやったり。
吉川 今のリアルってなんだろう?それをどう表現して伝える?こういうことを考えるだけでもこの時代ってものすごく深いかなって思います。僕が最近思うのは、例えばブランドが「今回のテーマはこれです!」って、僕も一生懸命やってたんですけど(笑)、毎回打ち出すけれど、他に伝えたいことがあるんだったら、それをやる必要はないんじゃないかなって。無理矢理テーマを作って、物語風に見せる必要ってあるのかな? テーマって必要なの?って発信する側として思うんです。
中川 コロナの今、テーマって別に、ですよね。
吉川 コロナがなくなっても、よく考えたら要らない(笑)
中川 わかります! 私はバーバリーの新しい広告にすごく感動したんですけど、黒人のダンサーたちが『雨に唄えば』をバックに、上から氷みたいなものが落ちてくる中で踊るというムービーに猛烈に感動して。バーバリーって白人のイメージがあったけど。
吉川 昔だったらありえないし、逆に昔からのことが今通用しないこともたくさんあるかも。
中川 そういう変化が私は好きです。ブラック・ライヴズ・マターとか、コロナがなかったらあれもなかったんじゃないかと思いますけど。だからこそ素晴らしいと思う。ダイバーシティ、イクルージョン、イクオリティ……。
吉川 世界中がそこに気づき始めて、でも苦しんでいますよね。次のステージに行こうとしてるのかな。
中川 地球は丸くてつながっていると、コロナが伝えてくれていますよね。丸くて、一緒にならないといけない。
吉川 あと、意外とちっちゃいぞって。
中川 確かにちっちゃかった。丸くてひとつなんだと教えてくれましたよね。
重くて苦しい、更年期のわたし

吉川 すべての人が自分の中に気に入らないところがあると思うんですが、中川さんがご自身で嫌いなことはなんですか?
中川 更年期のわたし、ですね。
吉川 そうか、更年期! それってきっと、多くの女性たちが四苦八苦しているとこだと思う。
中川 更年期のことを、みんな喋らないですよね。それがびっくりで。更年期というのは人生の避けられないプロセスの一つなのに、どうして私はこれほどまでに準備ができてなかったのだろうかと、不思議で仕方がないです。
吉川 居心地が悪いのはどこですか?
中川 体の痛み、不眠、記憶力の低下、身体中が渇いてくるような……、数え上げたらキリがないほど不調だらけ。作家の塩野七生さんが「コロナ渦の現在は、階段の踊り場。上がってきた階段から、次への階へ繋ぐ踊り場。踊り場は、息を整え、次のステージアップのためにある」とおっしゃっていましたが、女性の更年期も階段の踊り場のようなもので、これを乗り越えたら新しいステージが待っている気がします。
吉川 女性の体が劇的に変化する時ですもんね。生理が始まる時もそうですが、体も心も不安定になっていろんなことが不安になるし。だから更年期って女性にとっては第2の思春期みたいな感じなのかなあって僕は想像しているんですけど。
それらを解決するために何かしましたか?
中川 いろいろなお医者さまに会いに行きましたし、更年期の先輩や、いま更年期の友達、時にはばったり会った人にも片っ端から聞いてみたのですが、状況を劇的に変えられるコレという方法はないと納得するまでに、結構時間がかかりました。更年期は、これからしばらく付き合っていかなければならないパートナーのような感じです。
吉川 更年期とうまくやっていく。そういうお話しがもっと世の中に出てくるといいですよね。
内なる自分と向き合うために
中川 この更年期というパートナーとの関係をうまくやっていくのに一番効果的だと感じたのは、自分の体の声を聞き、その声に耳を澄ませることでした。
吉川 ご自身と向き合うためにしていることはありますか?
中川 走ることと、歩くことかな。コロナ禍で走ったり歩いたりする時間がたくさん作れて、去年は毎日5kmくらい歩いたり、走ったりしていました。あとは、アートを見たり音楽を聴いたり、本を読んで感動して満たされることが、自分を大切にするために欠かせません。
吉川 女性アーティストが好きとおっしゃっていましたが、今日お持ち頂いた本も女性アーティストのものですね。ジョージア・オキーフにシリア・ポール、ソフィ・カル。

中川 はい。彼女たちの作品や本に触れることで、エネルギーをもらいます。私の場合は気になったアーティストがいたら、彼女たちの生い立ちや、どうやってアーティストになったのかを調べるんです。だいたいが素敵な人格との出会いにあふれていて、やはり孤独です。彼女たちは他人と比較しはしないですし、自分で選んで行動して、はみ出していて、そして力強い。自分のおしゃれを持っていて、“個”を象徴する独特なおしゃれ感があると思います。
吉川 僕も男性のフォトグラファーと働いて女性のフォトグラファーと働いていると、個人個人の個性の違いはもちろん感じるんですけど、男と女ってやっぱり全然違うんだなっていうのも思うんです。その違いこそが女性であることの良さだと思うし、それは他のジャンルでも同じなんじゃないかな。
ところで今日は他にも愛用品をお持ちいいただきましたが、これはオイルですか?

中川 MAYUMIというブランドのスクワランオイルです。あるホームパーティで、本当に肌の美しいインド人女性に会って、彼女に何を使っているのか尋ねたところ、このスクワラン1本だけだと聞いてすぐに買いました。驚くほどサラッとしていて浸透性が高く、私もスキンケアはこれしか使っていません。
吉川 乾燥するニューヨークでもこれ一本でいけちゃうなんてすごいですね。
こちらの可愛らしい本は?

中川 工藤直子さんという詩人の詩集で、高校時代の友人が、わたしがアメリカへ留学する前にプレゼントしてくれました。音読するととても落ち着くんです。18歳から、何度となく引越しをしてきましたが、この本はいつも私と一緒です。18歳の時から、この本に支えられてきたのかな……。
人生の指針となった祖母の生き方
吉川 中川さんは今はニューヨークですが、『VOGUE JAPAN』にも在籍していたと聞いていますが。
中川 私は18歳からずっとアメリカにいて、36歳の時に『VOGUE JAPAN』を発行しているコンデナスト社のフォトエディターのお誘いを受けて帰国して、東京に9年ほど住んでいたんです。
吉川 9年は結構長かったですね。お子様は日本で、ですか?
中川 ええ。子どもが5歳になるまでいたんですけど、日本の学校に通うのはちょっと違うのかなと思って、それでNYに戻りました。
吉川 戻ってきてよかった?
中川 娘のためには自由な環境が良かったと思いますけど、日本人としてNYに住むのは戦いですよね。
吉川 そうかもしれない。
中川 でも後悔したくなかったから、また来ました。私の祖母が、今の私と同じ歳のときに隠岐の島という小さな島に幼稚園をつくったんです。
吉川 その時代にすごく活動的な女性だったんですね。
中川 島の子供たちに幼稚園という教育の場を持たせたいという一心で。彼女はいつも「容易い道と困難な道があるときは、困難な道を選びなさい」と言っていました。祖母の生き方から、年齢を重ねても自分の信念を貫くこと、後悔しないように生きることの大切さを教えてもらいました。
Photos / Interview : Yasuo Yoshikawa
Text : Tomomi Suzuki